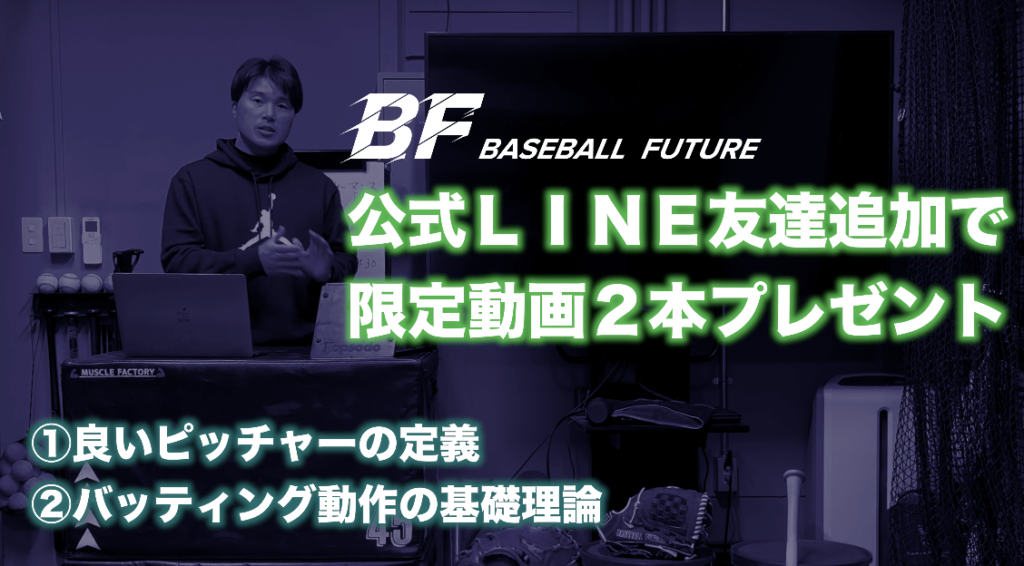バッティング・試合に向けた調整方法
こんにちは
BASEBALLFUTUREの
依田徹平です。

4月に入り新年度迎えBASEBALL FUTUREとしては2018年2月から活動を始めたので8年目の活動に突入しています。お陰様で現在では3店舗にて活動を続け選手のサポートをすることができています。これからも現状に甘えず選手、野球界のために貢献できるように真摯に取り組んでいきたいと思います。
さて高校野球では春の大会も始まり大学野球、プロ野球も開幕を迎えています。そんな中思うような結果を得られなかった選手やチームもすでにあると思いますが、アマチュア野球の場合夏に主要な大会が控えていることが多いのでこの反省を活かして夏に向けて進んでいくことが重要となります。
そこで今回は試合に向けたバッティングにおけるおすすめの調整方法を提案していきます。
速い球を練習してはダメ?
まず基本的な考え方としてバッティングは実力以上のものが出ることはあまりないと考えましょう。今回ここでお伝えする内容はいかに試合で実力を発揮できるかといった技術的なアドバイスになります。(メンタル面は除く)

「練習試合では同じレベルのピッチャーから充分な得点を奪えているのに、公式戦になると打線が振るわない」
こういったケースは私も経験がありますがよくあることです。
もちろん投手と打線の間に圧倒的な実力差があれば気にすることはないのですが、ある程度のレベルに達した投手を相手にした場合、打線の調整法を間違ってしまうと格下と思っていた相手にも苦戦を強いられてしまうこともあるでしょう。
特に今までよくみてきた主な調整方法のミスは投手の速いボールの対策としてマシンで速いボールを打ち込む練習を前日に行うこと。
速いボールを打つために速いボールで練習をするということは一見理にかなっているように感じます。実際速いボールを体感することでミート率が向上するといったデータもあります。しかしこれは目が慣れるという点では有効ではありますが、フォームのメカニクスが崩れていくというリスクが潜んでいると私は考えています。
ピッチャーに合わせて足を上げてテイクバックを行い並進運動からトップに入り回旋運動を行うのが大まかなバッティングのメカニクス。
素振りや、ティーバッティングなど様々なスキル練習で作り上げ調整したメカニクスは実に繊細なもので試合での1打席でよくも悪くも変化をしてしまいます。それはピッチャーと違いバッターは相手に合わせなければならないからです。

これはあくまで私の感覚ですがフリーバッティングは長くやればやるほどメカニクスは崩れていきます。特に何も意識せずにただ遠くに飛ばすことや強く打つことだけを目的としていると余計にフォームは崩れていきます。そのメカニクスの崩壊に追い打ちをかけるのがマシンでの速球対策です。
素振りやティーバッティングは自分の意識したフォームを自分のタイミングである程度行うことができるので調整には最適です。またバッティングピッチャーが投げた軽いボールを打つ程度であればピッチャーとのタイミングや感覚を試すためには必要ですし、メカニクスはそこまで崩れません。
しかしバッティングマシンを使った速球対策の練習はピッチャーが投げたボールとは違いノーモーションから速いボールが向かってきます。これによりバッターは反応が遅れ、その遅れを取り戻すためにメカニクスを崩してヒットを打ちにいきます。
この時はヒット性のあたりを打って満足をしてしまうのですが、いざ試合になるとピッチャーとのモーションにタイミングを合わせることができず、自身のメカニクスを崩してしまっているので対応ができなくなってしまうのです。
レッスンでも軽い手投げのフリーバッティングをよく行いますが、急に軽いボールに空振りを連発する選手は十中八九マシンバッティングを週末にしています。特に速いボールを打ち込んできた選手は全くタイミングが合わないのですぐに分かります。
当て感とは?
試合でのミート力が高い選手を「当て感が良い」と表現することがありますが、この当て感が良い選手はどこが優れているのでしょうか?
まず一つは先ほどのメカニクスが優れていることです。バットの操作力が高く遠回りせずに滑らかにボールの軌道にバットを出すことができるので思ったところにバットを出すことができます。さらに伸張反射を利用して素早くバットを振り出しタイミングを合わせることができています。
当て感がない選手はそもそもこのメカニクスが悪いか調整方法を間違えてメカニクスを崩してしまっている可能性があります。
そして2つ目はボールがどこに来るのかを予測する能力が高いということ。
思ったところにバットを出せてもボールの軌道がある程度正確に予測ができなければボールに合わせることができません。では一流選手は何をみてボールの軌道を予測しているのでしょうか?
おそらく多くの方がピッチャーがリリースした後のボールの軌道と答えることでしょう。これも間違いではありませんし、実際ボールの軌道は目で追わなければ打てません。しかし実際にはそれだけでは不十分です。なぜならば140km/hを超える速球を持つ投手の場合リリースからベース上に来るまで約0.4秒しかありません。これを目でボールの軌道を追うだけでは情報不足です。実は一流の打者ほどその情報不足をピッチャーのフォームから補っているのです。
リリースの角度や力感、胸の開きなど様々なピッチャーのフォームを無意識で捉え経験から予測を立ててボールの軌道予測に役立てているのです。
つまりマシンバッティングは試合とは全く異なる神経回路で動作を行っているのです。利点があるとすれば先ほども言ったように速いボールを目で追うことくらいです。
最適な調整法とは?
このことからおすすめしたい調整法は
・素振り
・ティーバッティング(スタンドティー)
・手投げフリーバッティング(遅い球)
・マシンを使ったバント練習(速球&変化球)
フリーバッティング後はまたティーや素振りで調整が必要

逆効果となる調整法は
・マシンを使ったフリーバッティング(速球)
・手投げフリーバッティング(短い距離からの速い球)
・連続ティーや連続素振り
よく考えてみれば分かることですがプロ野球でも試合前のフリーバッティングは手投げの比較的遅い球です。
それでも試合では150km/hを超えるピッチャーのボールをとらえています。
目が慣れることは大切ですがまずその前提となるメカニクスを崩さないようにすることを心がけましょう。
また連戦になると試合での打席が積み重なりメカニクスが崩れてしまうのでその都度調整を行うことが必要です。
個人的に最近マイナスだと思うことはプロ野球のオープン戦での打席の多さです。
期待のルーキーや助っ人選手がオープン戦で多くのチャンスをもらい打席を重ねますが、最初は好調でもそこがピークでシーズンが始まるとピッチャーのレベルも上がりますが、メカニクスも崩れてきているので全く打てずに2軍落ちというケースがよくあります。
逆にすでにレギュラーが確約されている選手はオープン戦終盤から打席が増え始めて調整をしシーズンにしっかりとピークを持って来れているように思います。
もちろん1年間シーズンを戦うためには年間を通して打席があるのでそんなことは言っていられないのですが、スタートダッシュさえ決まればもう少し我慢して起用できて戦力になるのにと思うことがあります。
WBCを制した2023年の大谷選手も大会前の実戦の打席は練習試合4〜5打席くらいで本大会に臨み結果を出していました。鈴木誠也選手もあるインタビューで1試合で3打席くらいしか集中がもたいないので3打席で変わっても良いというような趣旨を冗談半分で話していました。
この辺りの選手は独自の感覚から少ない打席でもピッチャーとの間合いやタイミングを掴めればあとはメカニクスを維持するだけで良いと分かっているのでしょう。
ぜひこれから大会を控えている選手やこの春うまくいかなかった選手、チームはこのような調整方法を試してみてください。
PS.
落合監督の現役時代もスローボールでのフリーバッティング調整と、オープン戦でボールを見るだけという有名な動画がありますのでぜひ参考に↓